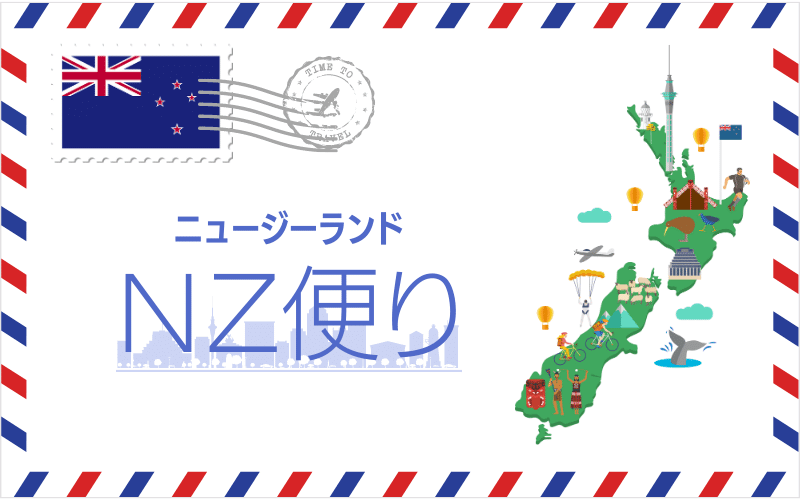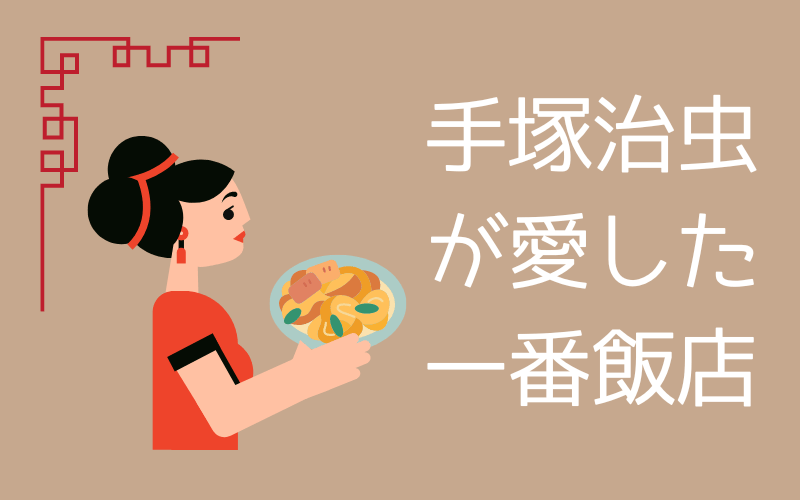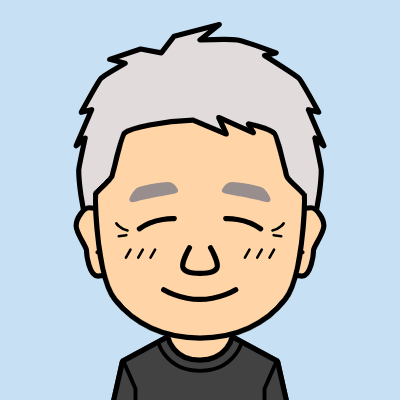
この「NZ便り」は、NZから日本の友人に宛てた手紙をまとめたものです。
ニュージーランドってどんな国?
6年間の駐在と多くの滞在経験を活かし、NZの魅力をお届けします。
<注記>
この記事は、2004年~2005年に書いたものです。現在のニュージーランドと異なる場合があります。予めご了承ください。
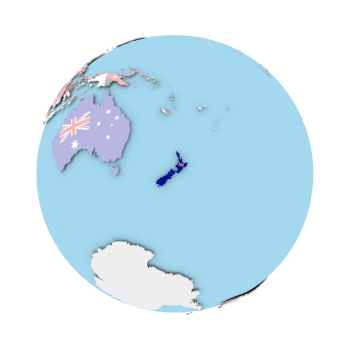
今回は、手紙を送っている貴方からの11の質問に答えたいと思います。
ニュージーランドの疑問?
Q1:ダチョウの飼育
日本などでは健康的な肉としてダチョウが飼育されていますが、NZでも「モア」の代替えとしてダチョウを商業的に飼う動きはありませんか?
ダチョウはよく知りませんが、鹿の飼育は盛んです。
脂肪分が少なく美容食だそうで、ドイツが最大の輸出先です。
私も駐在時代日本向けにトライしたのですが、日本人には鹿の肉はタブーのようでした。
また、牧場より逃げ出し野生化した鹿も南島の山には相当いるそうで、これを狙ったハンティングも盛んに行われているそうです。
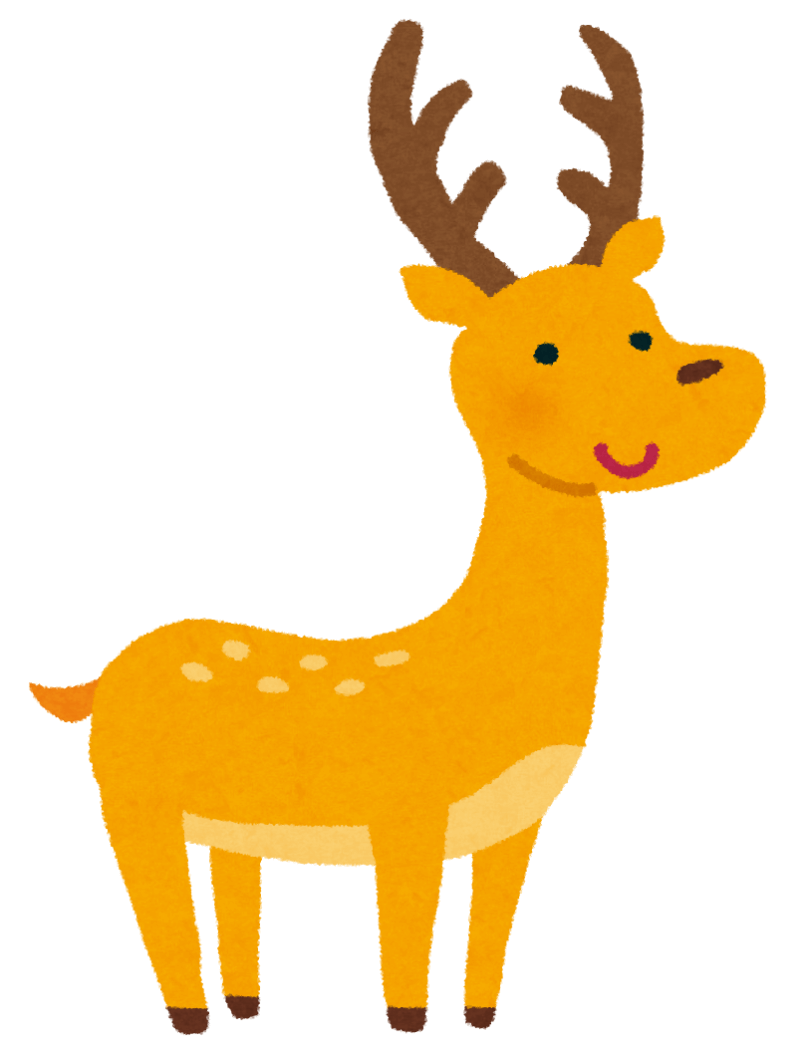
Q2:キーウィ
キーウィという鳥の名前は、フルーツにも使われていますが、ほかにもキーウィを使った言葉はありますか?
キーウィとはニュージーランドにしかいない鳥の名前で、なんといってもニュージーランドの象徴です。
皮の色と形がキーウィに似た茶色いフルーツをキーウィフルーツと言い、またニュージーランドの人をキーウィと呼びます。
「Are you a KIWI ?」と聞くと誇りを持って「Yes.」と答えます。
それにしても見かけは貧相な鳥です。
夜行性で目は退化して見えず、頭は毛が少なくなった老人のよう。
こんなことを言ったら叱られるかな・・・・。
余談ですがオーストラリア人のことをオージーと呼びます。
小さな島国のキーウィがオージーに対し一つだけ威張っていることがあります。
「俺たちはオージーのように囚人の子孫ではない」と。
昔英国は囚人をオーストラリアに島流しにしていました。

Q3:マオリ族
オーストラリアの原住民アボリジニーズは白人に手酷い仕打ちを受けたようですが、歴史上ニュージーランドのマオリ族は奴隷的な労働力にはならなかったのですか?
私は英国人の植民地政策を高く評価しています。
先住人と上手く共存し、その謙虚な態度が成功の秘訣ではと思います。
ホンコン・マレーシア・シンガポール等々に上手く入り込んでいきました。

Q4:島国の違い
NZには猛獣や毒蛇はいない。また白人が持ち込むまで「鹿・牛・羊」はいなかった、とのことですが同じ島国の日本と何故そんなに違うのですか。
ポッサムというねずみを少し大きくしたような動物がいますが、これも食用に持ち込まれましたが、北海道のキタキツネのように病原菌を持ったために食べられなくなりました。
天敵がいないため、これが全国に繁殖し、ハイウエーを走っているとあちこちにその死骸がころがっています。
夜飛び出し車のライトで動けなくなりひかれるそうです。
日本との違いは島の成り立ち方が影響していると思われますが、別の機会に調べてみます。
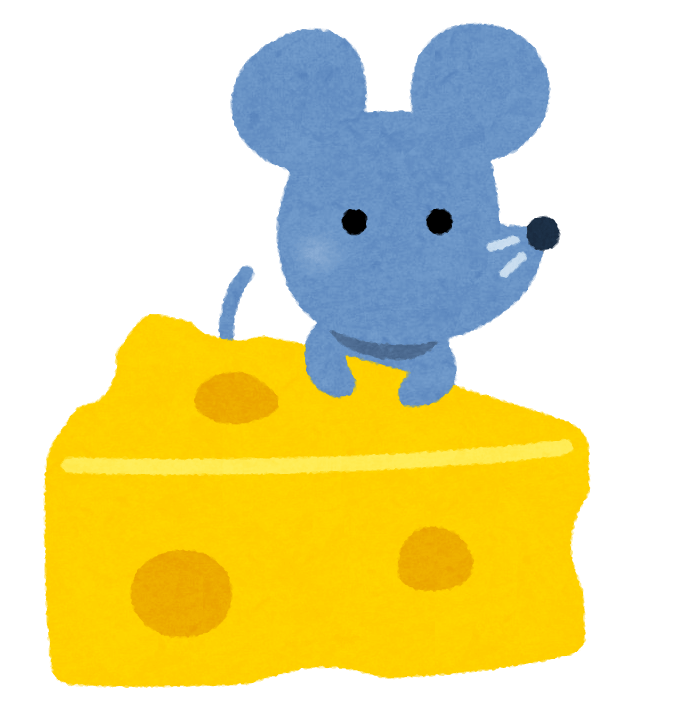
Q5:ニュージーランドの昼食
NZのオークランドには会社勤めのサラリーマンが多いと思いますが、昼食はやはりサンドイッチが多いですか?NZ特有の昼食は?ラーメンや寿司は少なく、中華は多いですか?
キーウィは昔から昼食は2~300円のサンドウィッチです。
それをオフィスのコーヒーと一緒に食べています。
しかし、最近は東南アジアからの移民が増え、フォッカーセンターのような所もあちこちに出来、500円くらいでおいしいものが食べられるようになりました。
また韓国人経営の日本食堂を真似た店がいたるところに目につきます。
寿司と称している「のり巻」は韓国でもよくたべるそうです。
ラーメン屋も多くなりました。
一杯700円位で、やはり日本人の経営の店は割高です。
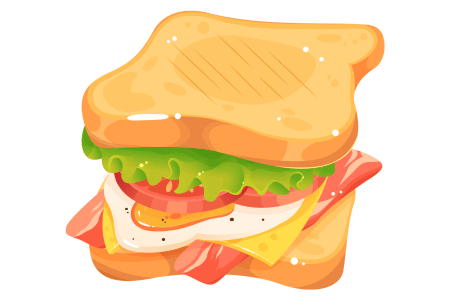
Q6:車
車は、アメリカ車よりもやっぱり英国車が多いですか?
車は断然日本車が多く、80%以上を占めていると思います。
10数年前までは日本の自動車メーカー各社が当地に組立工場を持っていましたが、400万人弱を相手にしては経営が成り立たず引き上げました。
今はそのための保護関税もなくなり、完成車の輸入が自由に行われています。
また、日本より中古車が比較的安く持ち込まれています。ただしあまりのオンボロは締め出されるため、製造後7年以上の車は許可されません。
こちらで人気のある車は、日本車ではトヨタ、意外に三菱も人気があり、ゼロ戦のエンジンを作った会社として高い評価を得ています。
もちろんベンツ・BMWは高級車として人気があります。

Q7:ニュージーランドの治安
NZの治安は良好と認識していますが、具体的に銃剣等の所持は日本と同様でしょうか。
銃剣等の所持は日本同様非常に厳しく規制されています。
しかし当地も近年物騒になりました。
私が駐在していた20年前には殺人事件などほとんどありませんでしたが、今回来てからも、新聞にもこの種事件がたびたび報じられていて恐ろしくなります。
車上荒らしなどは日常茶飯事です。
意外なことにドメスティック・ヴァイオレンス(家庭内暴力)もよく新聞を賑わしており、やさしい外面よりは信じられないことですね・・・・。

Q8:フィッシング
フィツシングは人気のあるスポーツなのですか?
フィッシングは盛んです。
海釣りにはボートやヨットで出かけますが、もう一つ鱒(マス)釣りがあります。
産卵に上る鱒を川で釣るフライフィッシングや、夏場、湖でボートから釣ったりしますが、鱒釣りは技術を要するため一部の釣りキチに限られるようで、また素人のガイドをして生計を立てているプロも大勢います。
こちらの鱒は日本で見る鮭位の大きさがあり、30cm以下は子供で、逃がさなければなりません。
また一日一人8匹までとの制限もあり、資源を大事にするのもNZらしいと思いました。
1mほどの鱒がかかったときの手ごたえ、そしてそれを吊り上げる醍醐味は、とても筆舌に尽くせません。

Q9:シーフードの食文化
日本のようなシーフードの食文化はNZにはありますか?
アングロサクソンはシーフードをあまり食べなかったためか、魚の料理は下手なようです。
従って昔は英国人の町にはステーキ屋はあっても魚料理はほとんどなく、レストランのメニューにも魚料理はありませんでした。
唯一、フィッシュアンドチップスが有名なだけで、これも魚とジャガイモを油であげただけの簡単なものです。
しかしニュージーランドにも近年各国からの移民が増え、おいしいシーフードが食べられるようになりました。
美容上魚を食べる人も増え、刺身をおいしそうに食べているキーウィもよく見かけます。
余談ですがフランス・イタリア・スペイン等のラテン系になるとシーフードを好み、料理もぐっとおいしくなります。

Q10:ニュージーランドの物価
NZの物価はどうですか。ビジネスホテルはありますか?
こちらの生活費は大雑把に言って日本の70%くらいです。
食べ物は安く、車やTVなどの工業製品は高くなります。
賃金は少ないが毎日の食費にかかる出費は低く、その分日本の生活よりリッチな気持ちになります。
ビール1缶70円、昼食代は街の食堂のバイキングで4〜500円、こちらの人はサンドイッチ2〜300円で済ませます。
ビジネスホテルというものはありませんが、モーテルなら1泊5〜7000円くらいです。モーテルにはレストランは無いが自炊の設備があり、駐車場付きです。
長期滞在者や、車で移動するビジネスマンがよく利用します。
こちらの人は物を大事にします。
シャツもズボンも色があせるまで着ています。
使い捨ての多い日本はもっと見習わなければと思ったりします。
日本に帰ると家内がよくこぼしていますが、こちらのスーパーなどに買い物に行くと3000円も出せば手に持てぬほど買えるのに、日本では少ししか買えないと。
ニュージーランドに来るとリッチな気分になるそうです。
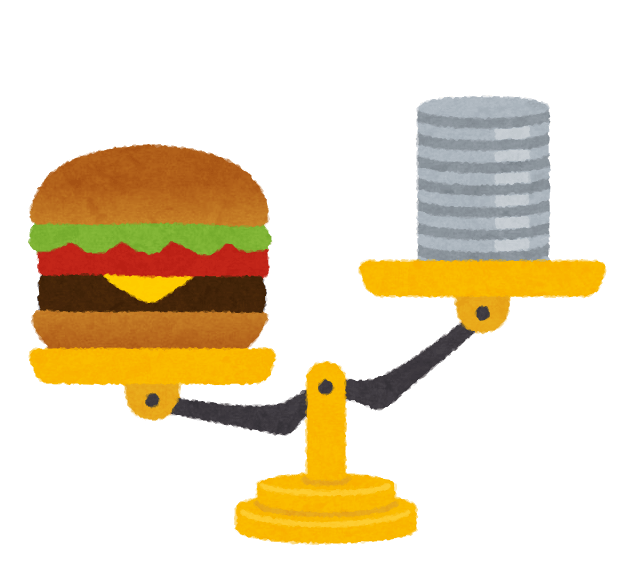
Q11:ニュージーランドで困ること
すべて良いことずくめのようですが、何か困ったことがありますか。
こちらの生活で何が足りないか考えてみました。
食べ物は安いし、人々は親切だし・・・・。
いい事尽くめの様ですが、何か満たされません。
それはやはり情報の不足のような気がします。
Sky TVでNHKがみられます。
しかし生放送とはいえ4時間の時差があり、朝8時のドラマは昼の12時になります。
夜9時頃の番組は深夜の1時になり、付き合うのは大変です。
しかも、私のような短期滞在者はSkyの契約(結構高い)をしていませんので、情報源は現地の新聞かTVになります。
新聞は何とか読めるとしても、TVは半分もわからない。
ドラマを見てもさっぱり判らず、一生懸命見ると疲れるだけでついつい見なくなります。
やはり語学のハンディーは決定的です。
その内日本のことはどうでもよくなり、浦島太郎になっていくようです。

Q&Aは、以上です。
最後に
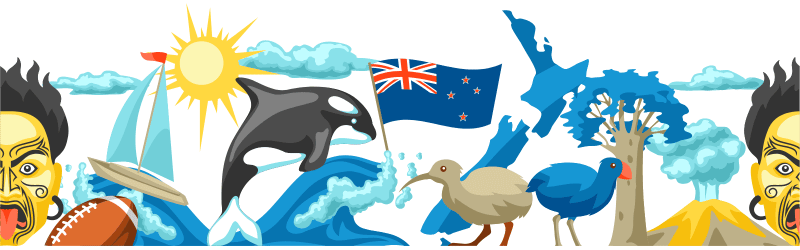
私のたわごとを長いことお聞きいただき有難うございました。
そろそろ帰国の日も近づいてまいりましたので、今回をもって終了とさせていただきます。
ニュージーランドは日本と正反対の南半球に位置しています。
そうだからではありませんが、すべてが日本と正反対のように思います。
日本の田舎は別として、そこには美しい自然があり、人が少ない。
通勤地獄はなく、物価は安い。
もっともカメラや自動車等の工業製品が高いことを我慢すれば、非常に住みやすいところだと思います。
こちらの人の給料等の収入は少ないかもしれませんが、出て行くものが少なく、リッチな感覚は日本の比ではないように思われます。
こんなNZに魅かれ、またやって来たいと思っています。

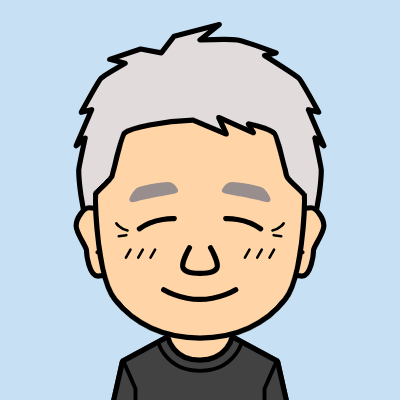
長い間のご愛読有難うございました。
私のつたない「NZ便り」で、一人でも多くの方がニュージーランドの良さを知り、一人でも多くの“ニュージーファン”が出来れば無上の光栄です。