最近は、住宅密集地でも薪ストーブの煙突を見かけるようになりました。
薪ストーブには、生活を豊かにしてくれる魅力が沢山ありますが、一方でデメリットも多いものです。
特に煙の臭いが問題になることが多く、自然に囲まれた場所とは異なる住宅密集地では近隣への配慮が必要です。
何とかなるだろうと楽観視していると後で大変な目に合うことに、、、
薪ストーブのデメリットをよく理解し、十分な対策を講じましょう。
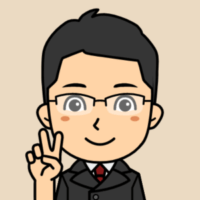
近隣への配慮と十分な対策を!
\住宅ローンを不動産任せにしないで!自分で出来る無料チェック!/
住宅密集地での薪ストーブの苦情対策
薪ストーブの煙突から出る煙の臭い

薪を燃やすと煙突から煙が出ます。
最近の薪ストーブは、炉に取り付けられた触媒によって煙をほぼ透明に変えることもできます。
しかし、煙が見えなくなっても、臭いは消えません。
乾燥した薪を使えば臭わないと言う人もいます。
けれども、木を燃やした時のいぶったような臭いは必ず漂(ただよ)います。
一方で、臭いは風に流されます。
風下に人が住んでいない田んぼや川があればリスクは低いように思えます。
しかし、実は、風下への臭いの心配よりも、無風の日の方が困るのです。
煙の臭いが残留しますので、近隣から苦情が出る恐れが高まります。
そのため、焚き始めた後も時々家の外へ出て、風と臭いの状況を確認することをおすすめします。
今日は、風が強いとか弱いとか、臭いが濃いとか薄いとか。
やはり、風が強い日のほうが臭いは薄まるように感じます。
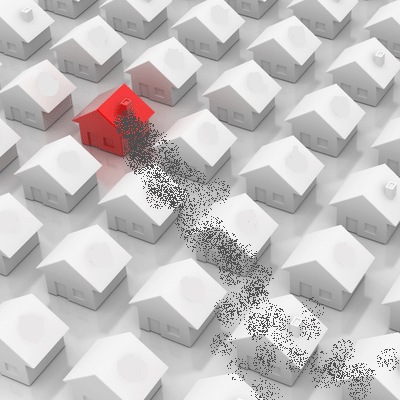
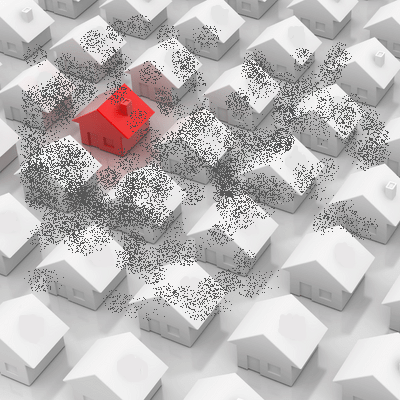
もうひとつ伝えておきたいことがあります。
薪ストーブのある家が近所に多いほうが、薪ストーブを使いやすいということです。
臭いの問題はなくなりませんが、その責任を複数の家で負いますので、かなり心強い。
家のまわりに煙突が何本あるのかを調べた上で、薪ストーブの導入を検討するというのも賢明と言えます。
住宅密集地での薪ストーブを使用する頻度
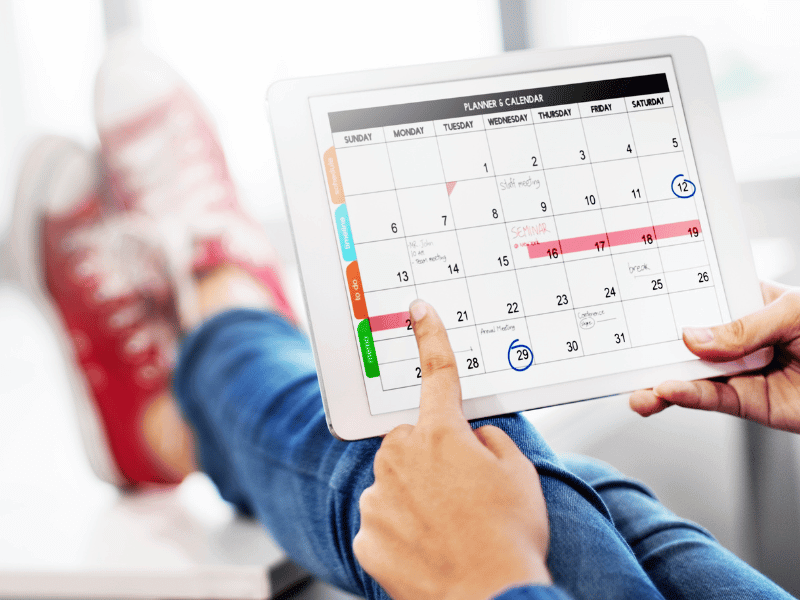
薪ストーブの臭いは、洗濯物に付きます。
そのため、隣の家が洗濯物を取り込んだ夕方過ぎから薪を燃やすようにしましょう。
さらに、燃やすのは土日だけとか、頻度にも注意する必要があります。
やはり、毎日臭うというのは、近隣にかなりのストレスを与えます。

しかし、冬の寒い日は、どこの家も窓を閉めてるから、外の臭いはわからないんじゃないの。
そう思われる方もいますが、窓を閉めていても、外の臭いは建物の中に入ってきます。
住宅に義務付けられた24時間換気の給気口から外気が侵入します。
繰り返しますが、薪ストーブを毎日使うのではなく、節度のある時間帯や頻度で使うように心掛けましょう。
住宅密集地での薪を割る音

薪割りは、薪ストーブの醍醐味でもあります。
しかし、斧で薪を割る音が近所迷惑になるケースもあります。
さほど大きな音ではありませんので、心配するまでもないのかもしれません。
普段から近隣と良好な関係を築いていれば、さほど問題にならないでしょう。
薪ストーブの煙突掃除でのススの噴き出し

年に一度、煙突の中を掃除します。
屋根の上にのぼるのは危険ですので、煙突下の掃除口からブラシを挿入し、上へ押し上げながら煙突内に付着したススやタールを取り除きます。
注意すべきは、頂部にブラシが達した際に、ススが上から噴き出すことです。
このススが、隣の家の屋根やバルコニーを汚すことがあります。
煙突の掃除をすることを事前に断ってからはじめることをおすすめします。
薪ストーブの煙のにおいのまとめ
以上、住宅密集地で苦情になりやすい薪ストーブのデメリットについて説明しました。
対策をまとめると、
・煙が透明になる触媒タイプ(触媒の効果についてはこちら)を選ぶ
・煙の少ない乾燥した薪を使用する
・風が強い日を選ぶ
・近所に煙突が複数あれば心強い
・毎日の使用は控える
・薪割りの音に注意
・煙突掃除時の頂部からのススの吹き出しに注意
となります。
残念ながら住宅密集地での薪ストーブの使用は難しいものです。
しかし、薪ストーブの暖房能力は、家電製品とは比較にならないほどハイパワーであり、魅力的です。(薪ストーブの暖房能力については、こちら)
日頃から近隣とのコミュニケーションを良くし、迷惑にならない程度に楽しむことをおすすめします。
\あなたの住宅ローンが毎月1万円変わる。自分で出来る無料チェック!/



